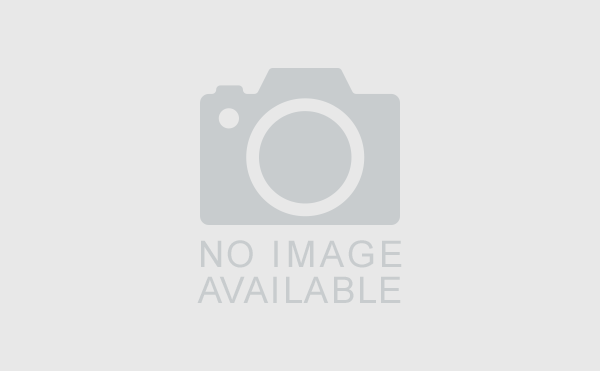労使間に黙示の職種限定合意があったことを認め,使用者側は配置転換を命ずる権限を有していなかったとしたとして原審に差し戻した事案(最判令和6年4月26日・労働判例1308号掲載)
1 事案の概要
本件は,被上告人に雇用されていた上告人が,被上告人から,職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため,同命令は上告人と被上告人との間でされた上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして,被上告人に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等をした事案である。
2 裁判所の判断
一審判決は,黙示の職種限定合意は認めつつも,上告人が担当していた業務が減少し,会社が最終的に当該業務をやめたという事実関係の下で,上告人の解雇を回避するためには,上告人を退職者が出た部署に配転することにも業務上の必要性があるというべきであり,それが甘受すべき程度を超える不利益を上告人にもたらすものではなく,会社に不当な動機や目的があるとも認められないとして,配転命令は権利の濫用に当たらず,違法・無効ということはできないとしました。二審判決もこれを支持しました。
これに対し,最高裁判決は,次のとおり判示しました。労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上告人と被上告人との間には,上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから,被上告人は,上告人に対し,その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。
そうすると,被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき,被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として,その濫用に当たらないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
なお,差し戻し審は,不法行為を認め,80万円の慰謝料を認めました。
3 コメント
使用者の配転命令権については,就業規則等に包括的規定が置かれている場合が多いですが,このような規定がなくても労働契約締結の経緯などから使用者に配転命令権が認められる場合があります。もっとも,使用者が自由に配転命令を行うことができる訳ではなく,権利の濫用と判断されれば違法・無効となります。権利の濫用になるか否かは,業務上の必要性や人選の合理性,労働者の受ける不利益の程度等を総合考慮して判断することになります。
一方で,職種や勤務地を限定する形の労働契約が結ばれることがありますが,職種や勤務地が限定される形の合意が成立している場合は,原則として,使用者にはその範囲でしか配転命令権は認められません。なお,職種や勤務地の限定については,明示の合意がなくても本判決のように黙示の合意が認められる場合があります。黙示の合意が認められるかどうかは,職種の専門性や採用の経緯,勤務実績等を考慮して判断することになります。
労使間に職種や勤務地について限定する合意がある場合は,使用者が労働者を配転させるためには労働者の同意が必要となります。しかし,本件のように,職種限定のなされた職種を廃止せざるをえないような場合は,配転することも許されるとした裁判例があります。本件の一審,二審も,労働者の担当していた業務の廃止の事実等による配転の必要性のほか,労働者の不利益が大きくないことや使用者に不当目的がないことを認定し,使用者に配転命令権があることを前提に配転命令が権利の濫用に当たらないとしました。最高裁は,この一審・二審に法令違反があるとして原審に差し戻しましたが,職種限定がある場合に配転命令が一切許されないとするものかどうかは判断が難しいところです。
(2025.4.6)