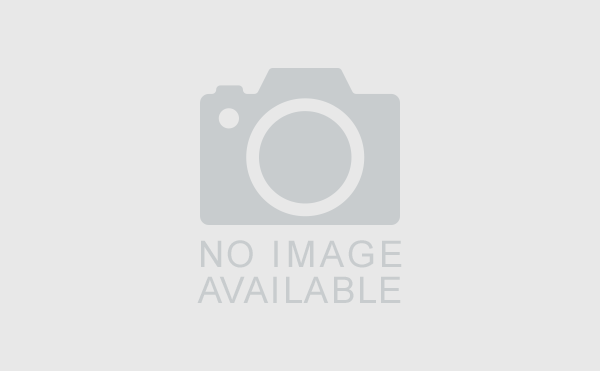労働者派遣について
1 労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要となります。そして、派遣元会社の労働者の雇用形態には、無期雇用型と有期雇用型があります。平成27年の法改正前は、労働者派遣事業の区分(届出制特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業)の関係でいわゆる登録型派遣と常用型派遣に分けられていましたが、法改正により全てが許可制となったことから、法律上は無期雇用派遣と有期雇用派遣に分けられます。
なお、登録型派遣とは、派遣元企業に登録をしておいて、派遣先企業と派遣元会社間で結ばれる派遣契約期間中に限って雇用契約を結ぶ有期雇用の形態で、派遣契約期間が終了したら、雇用契約は終了となります。
常用型派遣とは、派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用であって1年以上継続して雇用される者又は1年以上雇用する予定のある者との契約形態で、派遣先企業での就業期間が終了しても、派遣元との雇用契約は契約期間中存続します。
そのほか、紹介予定派遣があり、これは、派遣先の企業に直接雇用されることを前提とするもので、派遣期間は最大6カ月となります。派遣期間中に派遣社員と派遣先企業双方の合意が得られた場合はそのまま直接雇用となります。ただし、直接雇用の形態が正社員になるとは限りません。
2 労働者派遣事業の適用除外業務
以下に該当する業務の労働者派遣事業を行うことはできません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合、産前産後休業等を取得した労働者の業務である場合や医師の業務であって就業の場所がへき地にある場合を除く。)
(5)その他
・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士ほか8資格の業務
・建築事務所の管理建築士の業務
3 派遣先における期間制限
平成27年の労働者派遣法の改正により、施行日である平成27年9月30日以降に締結又は更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。ただし、クーリング期間があります。
(1)派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は原則3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(2)派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(課等)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
(3)例外
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)
・日数限定業務(1か月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)
・産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
4 日雇派遣(30日以内)の原則禁止
原則として、日雇労働者(派遣元事業主との労働契約が30日以内の労働者)を派遣することはできませんが、以下の例外があります。
(1)日雇派遣の例外業務
ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍などの制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業、社会福祉施設等における看護業務、
(2)日雇派遣の例外の場合
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として従事する人(生業収入が500万円以上の人に限る)
・主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上の人に限る)
5 その他平成27年改正及び平成30年改正の主な内容
(1)雇用安定措置
派遣元企業は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じる必要があります。具体的には雇用状態に応じて、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元企業による無期雇用、④その他雇用の安定を図るために必要な措置をとる義務又は努力義務が課されています。
(2)キャリアアップ措置
派遣元企業は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。
(3)派遣労働者の同一労働同一賃金
・派遣元企業は、派遣労働者について、派遣先企業の通常の労働者との均等・均衡待遇、または一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを行う義務があります。
・派遣先企業は、通常の労働者の待遇に関して派遣元企業へ情報提供をする義務がありま
(4)派遣労働者に対する説明義務の強化
派遣労働者が不合理な待遇差を感じることのないよう、雇入れ時、派遣時、派遣労働者から求めがあった場合の派遣労働者への待遇に関する説明義務が強化されました。
(5)裁判外紛争解決手続の規定の整備
派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、企業と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続きが整備されます。
(2025.4.5)