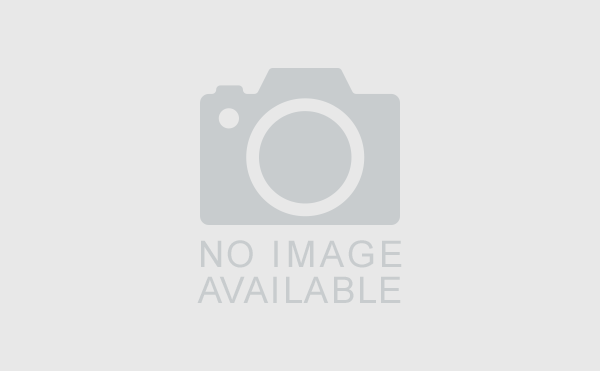区分所有法59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者が死亡した場合に,同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないとしてした裁判例(大阪地判令和6年9月5日)
1 事案の概要
本件は,ビルの管理組合の理事長がビルの区分所有者であった者に対し,区分所有法59条1項に基づき,当該区分所有物件の競売を求め,これを認容する判決が出されが,競売開始決定前に当該区分所有者が死亡していたことが判明したことから,競売開始決定を取り消した事案。
2 裁判所の判断
区分所有法59条1項に基づく競売(以下「59条競売」という。)は,競売請求権の存在を証する確定判決が提出された場合に限り,開始すべきこととされている(法59条,民事執行法195条,181条1項1号)。59条競売の開始決定前に,当該確定判決で被告とされていた区分所有者が死亡した場合,当該区分所有者は59条競売の当事者とはなり得ないから,当該確定判決に基づき59条競売を申し立てるためには,当該確定判決の効力が当該区分所有者の承継人(相続人又は相続財産法人)に対しても及ぶ必要がある。
そこで検討すると,59条競売は,特定の区分所有者による共同の利益に反する行為により,共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難である場合に,当該区分所有者の区分所有権を剥奪して同人を区分所有関係から排除することにより,その障害を除去することを目的とするものである(法59条1項,57条1項,6条1項)。そして,59条競売を請求する訴訟(以下「競売請求訴訟」という。)においては,当該区分所有者が上記のような属性を有するか否かが審理の対象となるが,そのような属性は,当該区分所有者固有のものであって,その承継人に受け継がれる性質のものではない。また,上記のような59条競売の目的は,区分所有者が変われば,達せられることになる。
このような59条競売の性質に鑑みれば,競売請求訴訟の口頭弁論終結後に区分所有者が死亡した場合,当該区分所有者に対する確定判決の効力は,その承継人には及ばず,当該確定判決に基づいて59条競売を申し立てることはできないと解すべきである。
これを本件についてみると,前記のとおり,相手方は,本件訴訟の口頭弁論終結後に死亡しているから,本件判決に基づいて59条競売を申し立てることはできないというべきである。
そして,本件決定は,上記の点を看過して本件判決に基づきなされたもので,この点につき重大な瑕疵があるというべきであるから,職権によりこれを取り消すのが相当である。
3 まとめ
本判決は,区分所有法59条が競売を認めた趣旨に立ち返り,当事者が死亡した場合は,その判決の効力は承継人には及ばないとしたものです。なお,最判平成23年10月11日判決では,確定判決後に区分所有権を第三者に譲渡した事案で,判決の効力は譲受人に及ばないとして競売申立てはできないとの判断を示しています。
確かに,区分所有法59条は,区分所有者の管理方法等(属性)に着目して競売を認めるものなのでやむを得ないとも考えられますが,承継人が同居している配偶者等の場合等は,同様の管理状態が続くと可能性も高いと考えられるので,迂遠な感じもします。
なお,区分所有法59条の競売がなされた場合,競売のための費用については競売代金から支払いを受けられますが,未払管理費等は競売代金から回収するのではなく,区分所有法8条の規定に従って新しい区分所有者から回収することになります。
また,競売の申立は,訴訟を提起して競売を認容する判決を得てから,これに基づき6カ月以内に行う必要があり,予納金も必要となります。
(2025.4.2)