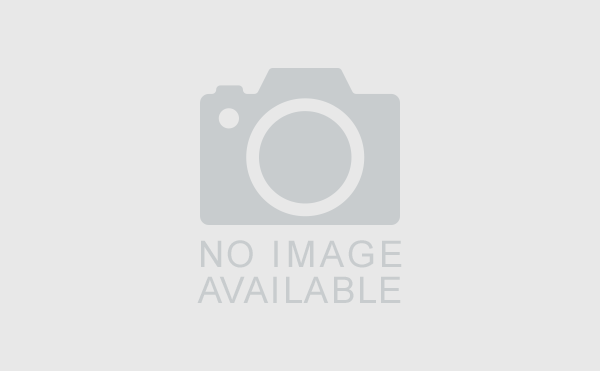収益物件の売主及び仲介業者に漏水や水道管の違法接続等について調査,説明不足の過失があったとして買主の不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事案(東京地判令和5年3月23日)
1 事案の概要
本件は,収益不動産を購入した事業者が,収益不動産としての経済的価値の評価を誤らせる重大な事象があったとして,売主及び仲介業者に対し,共同不法行為に基づき損害賠償請求した事案です。
主たる争点は,売主及び不動産仲介業者が①一部賃借人の退去,②漏水,③シロアリ被害,④水道管の違法接続について調査,説明しなかったこと等についての過失の有無,⑤損害,⑥過失相殺です。
2 裁判所の判断
宅地建物取引業者の過失判断基準として,宅地建物取引業者がその業務を行うに当たっては,委託を受けた者に対してのみならず,業者の介入に信頼して取引をするに至った第三者に対しても,業務上の一般的注意義務があり,この注意義務違反により当該第三者が損害を被ったときは不法行為責任を負うと解すべきである(最高裁第二小法廷判決昭和36年5月26日民集15巻5号1440頁参照)。
(1)一部賃借人の退去について
ア 売主の責任について
売主が一部の賃借人の退去を認識していたかは明確でないが,買主が賃料収入の情報を基礎に物件の購入を決めたことは容易に認識し得たことから,当該賃借人の賃料収入の状況等を売買契約締結前に確認すべきであったといえるところ,これをしていないことに過失があるといえる。
イ 仲介業者の責任について
売主が提示したレントロールに,一見して不審な点がないこと,また現地調査において,郵便受けに郵便物があふれていないか,各部屋を外部から確認していることに鑑みると,本件で,当該賃借人に照会する等の義務があったとまで言いがたい。よって,本件において,レントロールが誤っていたことについて,過失はない。
(2)漏水について
ア 売主の責任について
売主が物件のうち2室に漏水が生じていたことを認識していたのであるから,少なくとも当該2室については,買主原告に説明すべきところ,物件状況等報告書に記載がなく,売主には,漏水の事実を隠蔽する故意,ないし少なくともこれを失念して原告に伝えなかったことに過失がある。
イ 仲介業者の責任について
仲介業者の担当者が,売買契約締結前,物件の空室を確認し,一部の部屋で雨漏りによる跡を確認しているのであるから,売主に確認するだけでなく,管理を受託している会社に部屋の漏水の有無等について確認することは可能であり,容易であったといえ,更には,物件が,瑕疵担保責任免除特約を付されている以上,売主側仲介業者として,売主だけでなく管理会社にも確認をすべき義務があったといえる。しかし,確認をしていないから,仲介業者には,漏水に関する調査義務を怠った過失がある。
(3)シロアリ被害について
ア 売主について
部屋に虫の死骸があることを確認したが,虫の死骸については,窓から入り込んだものと認識することが不自然であるとまで言えず,売主が白アリ被害を認識していたことを推認させる事情は認められず,説明しなかったことに過失はない。
イ 仲介業者について
仲介業者は,部屋の一部に,虫の死骸を確認し,売主に説明を求めているが,その他にシロアリ被害が生じていることをうかがわせる事実は認められず,売主の窓から侵入した虫であるとの説明が不合理とまでいえないことから,仲介業者に売主に確認する以上に調査すべき義務があったとは言えず,過失はない。
(4)水道管の違法接続について
ア 売主について
宅内図と異なる直結給水方式が利用され,売主が東京都給水条例4条の手続を履践したことも認められず,違法状態であることは認められる。東京都給水装置工事事業者以外の工事業者に貯水槽水道方式から直結給水方式に変更する工事をさせることが同条例違反となることは認識していなかったようである。しかし,給水設備の方式は,東京都の設備と接続する部分であるところ,東京都に対し何らかの手続きを要する可能性があることは容易に想定し得るといえるが,売主が東京都に照会を行った形跡はない。また,売主が,貯水槽を清掃していないことを伝える過程で,これが直結給水方式にしているためであることを伝えるのが通常であるところ,これをしていないことに鑑みると,方式変更に問題があるとの認識をしていたことが推認される。よって,売主には,同方式の変更を原告に伝えなかったことに,少なくとも過失がある。
イ 仲介業者について
仲介業者の担当者が売買契約締結前に宅内図を取り寄せていること,貯水槽から各部屋に配管が接続されていることを確認したことは認められるが,配管が通路の階段上を這っていることをもって水道管が直結給水方式に変更されていることを認識可能であったとは言いがたい。また,仲介業者が,直結給水方式への変更を認識していなかった以上,貯水槽の中の状態を確認すべきであったとまで言えない。よって,水道管の違法接続に関し,仲介業者に,宅内図や売主に対し確認する以上に調査すべき義務があったとはいえず,過失はない。
(5)過失相殺について
買主は,代表取締役をしている法人において,投資用不動産と考えられる不動産を所有している。また,今回購入した物件は,築34年で法定耐用年数を経過していることから,経年劣化や本件で判明した漏水やシロアリ被害等の可能性があることは,買主自身も認識可能であったといえる。加えて,瑕疵担保責任免除特約を承諾している以上,買主も,仲介業者の担当者と共に空室を確認し,気になる点に説明を求めているのであるから,少なくとも買主が和仲介業者にも相談し,調査をすべきであったといえる。そして,買主と売主らの過失を比較衡量すると,買主と売主との間では,5割を買主の損害から減額し,買主と仲介業者との間では,7割を買主の損害から減額するのが相当である。
3 小括
本判決は,売主と仲介業者について,別々に責任の有無を検討しています。仲介業者の第三者に対する責任の有無の判断については,最高裁の判決を引用し,漏水についての調査義務違反のみ認めました。仲介業者は,売主ほどの情報は持っていないことから,売主の説明に不合理なところがなければ,独自の調査をせずに売主の説明を信じて買主に伝えたとしても過失はないと判断したものと考えられます。漏水についてのみ仲介業者に過失責任を認めたのは,物件の状況についてより詳しく把握している管理会社へ確認することが容易であったことから,その程度の義務を負わせることは過度な負担とはならないと判断したものと考えられます。また,漏水はその原因については専門的知識が必要であることから,専門的知識のない売主の説明を安易に信じて済ませたことについて問題があると考えたものと思われます。
なお、最終的に買主に5割以上の過失があるとして過失相殺しています。これは、買主が収益物件を所有する法人の代表を務めていたことから、一定の知見を有していたであろうということだと思いますが、買主に5割以上の過失を認めるのが相当かは疑問があります。
(2025.4.12)