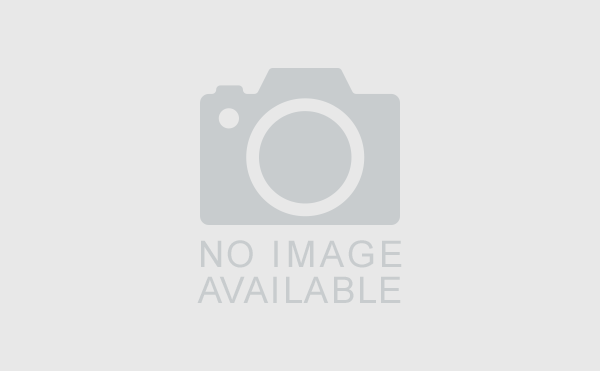サクイクリングコースをサイクリング中に溝にはさまって転倒した者の市に対する国賠請求が認められた事案(千葉地判令和5年7月19日)
1 事案の概要
本件は、サイクリングコースをロードバイクで走行していた者が、舗装路と土留めの間にできていた溝に自転車の前輪が嵌まり、転倒して負傷したと主張して、サイクリングコースの設置管理者である市に対し、国家賠償法2条1項による損害賠償請求をした事案です。なお、溝は、進路方向左側にあり、幅約2.9cm、深さ約10cm、長さ約10mでした。
主たる争点は、①事故の発生の有無、②設置・管理の瑕疵の有無、③過失相殺、④損害の内容です。
2 裁判所の判断
(1)事故の発生の有無
原告の主張が一貫しており、被告に連絡して現場で事故の発生状況を説明していることなどから事故の発生を認めました。
(2)設置・管理の瑕疵の有無
国賠法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断される(最高裁昭和42年(オ)第921号同45年8月20日第一小法廷判決・民集24巻9号1268頁、最高裁昭和53年(オ)第76号同年7月4日第三小法廷判決・民集32巻5号809頁参照)。
本件コースは、サイクリングのために設けられた、舗装されたコースであるところ、一般に自転車の車輪の幅は広くない上、自転車にはロードレース用自転車(ロードバイク)のように、通常よりも車輪の幅の狭い自転車もあることは公知であることからすれば、ロードレース用自転車(ロードバイク)も含め、自転車が通常の走行をする限り、安全に走行できる状態になっていなければ、通常有すべき安全性を欠くものとして、国賠法2条1項の「瑕疵」があるものというべきである。
本件溝は、本件コースの舗装路部分にあったものではないが、土留め上のフェンスの数十cm内側にあるなどの本件事故の現場付近の状況からすると、自転車が、歩行者や他の自転車とすれ違う際に接触を避けようとして、本件溝付近を走行することも十分に想定されるといえる。また、本件溝の幅は本件事故現場付近では約2.9cmであり、自転車の車輪の幅によっては本件溝に嵌まって事故が発生することも想定される。
以上によれば、本件コースに本件溝があることは、サイクリングコースが通常有すべき安全性を欠くものと認められ、他方で、被告において、本件コースの通常の用法等に鑑み、本件溝付近を自転車で走行する原告の行動により本件事故が発生することを予見できなかったということはできない。したがって、本件コースに本件溝があることは、国賠法2条1項の「瑕疵」に該当する。
(3)過失相殺について
原告は、自転車でロードコースを走行するに当たり、走行の障害となるものの存否に十分注意し、走行路面の状況に変化があった場合にも制御することができるように走行する注意義務があると解されるところ、本件においてはこれを怠った落ち度があり、その内容や程度に鑑み、1割の過失相殺をするのが相当である。
(4)損害の内容について
後遺障害については、原告の12級の主張に対し、他覚所見がないとして14級とし、逸失利益の生じる期間は5年限りで認めた。その他、文書料、治療費、休業損害(過去3か月間の支給額を稼働日で除して、1日当たりの額を算出)、交通費等の通常認められる損害を認定した。なお、物損については、一部については証明がいとして、一部については購入額が定額で一定期間経過しているとして認めなかった。
3 まとめ
国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求は、道路の瑕疵や公園の遊具の瑕疵など色々な場面で考えられますが、本件は、サイクリングコースの瑕疵に関するものです。サイクリングコースは自転車走行を目的に設置されたものですので、それを前提に瑕疵の有無が判断されています。なお、一般道路のくぼみやグレーチング(道路脇の側溝等に使用される鋼材が格子状に組まれた排水性のある金属製の蓋)の設置の不具合等による自転車の事故で国家賠償法2条1項の請求が認められたものもあります。
(2025.4.12 判タ1520号掲載)